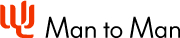2025年8月1日テクノロジー
どっちが勝つ?「電気 vs 水素」
電気自動車(EV)とは?
【強み】
☆充電スポットの増加などインフラが広がってきている。
☆エネルギー効率が高いので水素より少ないエネルギーで走ることができる。
☆パーツが少ないためメンテナンスが少なくて済み、静かで音も小さい。
【課題】
★充電時間が長く、急速でも数十分〜1時間かかる。
★バッテリーが重くなりがちなので長距離トラックには不向き。
★再生可能エネルギー(太陽光や風力等)との連携が天候や時間帯に左右される。
水素燃料電池車(FCVまたはFCEV)って何?
【強み】
☆充填が速く、ガソリンと同じくらいの短時間で済む。(3分〜5分)
☆走行距離が長い、中にはフル充填で600kmを超えるものも。
☆グリーン水素※1であればCO₂フリー。
※1 グリーン水素:太陽光、風力などの再生可能エネルギーから作られる水素
製造から使用まの過程でCO₂を排出しないのが大きな特徴
【課題】
★水素ステーションが少なく、日本全国で約160か所しかない。(2025年時点)
★水素の製造や運搬が容易ではなくエネルギーロスが多い。
★技術がまだ高コストのため車両価格が高い。

じゃあ、結局どっちが勝つの?
【現時点】
◆インフラとコスト面から乗用車はEV優勢。
◆バス、トラック、船、鉄道など大型や長距離は水素の可能性あり。
◆国や地域によって方針が異なる⇒欧州や中国はEV、日本や韓国は水素にも期待
【将来は】
EVと水素の「共存」が濃厚のようです。たとえば…
◆都市部や近距離 ⇒ EV
◆物流や公共交通 ⇒ 水素
◆航空や船舶 ⇒ 水素や合成燃料

「日本=技術大国=EV先進国のはず」?
と思われがちですが、実はかなり遅れているのが実情です。
では、なぜ日本のEV普及が遅れているかというと…
① ハイブリッド(HV)信仰が強すぎる
プリウスをはじめとするHVがかなり成功したため「EVじゃなくてもエコでしょ?」という空気がある。トヨタ、ホンダ、日産…主要メーカーが長年HV推しだった結果「EVにしなきゃ」という国民の危機感が薄い。
② 充電インフラがまだまだ
急速充電スポットは増えてきてるが欧州や中国に比べて少ない。マンションや団地など集合住宅では設置しにくく都市部で不便。
使える充電器が車種によって違うという問題(CHAdeMO vs CCS※2)も。
※2 CHAdeMOは主に日本メーカーで採用、DC充電専用のコネクタを使用
CCSは主に欧米メーカーで採用、AC/DC両対応のコネクタを使用
CCSの方が高速充電が可能で80%充電まで30分以内、CHAdeMOは1時間以内
③ 政策の後押しが弱かった
欧米&中国:補助金、税制、規制で一気にEVシフト
日本:比較的中立で「エンジン車も悪くない」という姿勢
⇒ユーザーもメーカーもEV投資に慎重
④ 「走行距離の不安」が根強い
日本人は通勤距離が短くても「電欠※3が怖い」という心理的ブロックが強い。
実は1日50kmも走らない人が大半だけど、それでも「500km走れないと不安」と感じてしまいがち。
※3 電欠:バッテリーの残量がゼロになり走行できなくなる状態、ガソリン車でいうガス欠
⑤ 車文化の違い
欧米&中国:車=移動手段(実用性重視)
日本:車=趣味、ステータス(走り、内装、ブランド重視)
⇒「無音、スムーズ」が魅力になりにくいある一定の層が存在
でも、最近は変わり始めている
日本国内では日産「サクラ」(軽EV)がヒットしたことから軽のEVに可能性を見出しており、政府も「2035年までに小型車の新車販売はすべて電気自動車※4に」の目標を掲げています。
※4 プラグインハイブリッド車(PHV)、ハイブリッド車(HV)、燃料電池車(FCV)なども含む
また、電気とモーターで動く電動バス(EVバス)が少しずつ広がっていますが、多くは中国のBYDや韓国の現代自動車といった海外企業が製造した車両。台湾の鴻海精密工業も2027年までに日本でEVバスを展開する方針です。
そこで、いすゞ自動車と日野自動車の合弁会社「ジェイ・バス」や新興企業のEVモーターズ・ジャパン(北九州市)といった日本勢が巻き返しを図ろうと自社生産に本腰を入れ始めました。

日本EVのこれから
商用車や配送業界ではすでにEV導入が進行中です。今後は都市部や軽自動車を中心にEV普及がより進むかもしれません。
また、水素とのハイブリッド社会も視野にあるようです。
どちらが“勝つ”というよりは「用途によって使い分ける」というのが現実的な見方ではないでしょうか。