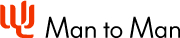2025年8月29日健康
ヘッドホン難聴に気を付けて!
外に出るとイヤホンやヘッドホンを付けている人を沢山見かけます。
これを読んでいるあなたも思い当たる節ありませんか?
現代病としてヘッドホン難聴というものがあります。
イヤホンやヘッドホンを長時間・高音量で使い続けることで聴力が低下する「騒音性難聴(そうおんせいなんちょう)」の一種です。
音楽プレイヤーやスマホの普及により、特に若年層で増加傾向にあり、「若年性難聴」とも言われることがあります。

なぜ難聴になるの?
内耳(ないじ)にある「有毛細胞(ゆうもうさいぼう)」という細胞が、音の振動を電気信号に変換して脳へ伝えています。
しかし、大音量の音楽や長時間のヘッドホン使用によって、これらの有毛細胞が疲労・損傷・死滅してしまい、聴覚情報が脳に届かなくなってしまうため音を正しく感じ取れなくなるのです。
内耳の有毛細胞は、音を感じ取るための非常に小さくて繊細な感覚細胞で聴覚の中核を担う重要な細胞です。
有毛細胞の再生はするの?
現時点では、ヒトの有毛細胞は一度損傷・死滅してしますと、自然には再生しないとされています(※一部動物では再生することが確認されているため、再生医療の研究が進んでいます)。
有毛細胞は非常に特殊な細胞で、一生のうちに生まれ変わらない性質があります。
原因
ヘッドホン難聴の原因はいくつかあります。
・長時間の使用:毎日長時間音楽や動画をヘッドホンで聴くことで、内耳の有毛細胞が疲労・損傷します。
・大音量:大音量で音楽を聞くと、耳の奥の感覚細胞に強い負担がかかります。
・遮音性の低い環境:周囲の騒音をかき消すために音量を上げてしまいがちです。
・体調:強いストレスや疲労が溜まると血流を悪化させ内耳の血流不足を引き起こすことがあります。
症状
・高音が聞き取りづらくなる
・耳鳴り(ピーやキーンという音など)
・会話の中で言葉が聞き取りにくくなる
・両耳または片耳の聴力低下
・聞き取りにくさがストレスとなり集中力・注意力が低下
進行の特徴として、初期には自覚症状が少なく、気づいた時には重症化していることも。
また、一度失った聴力は基本的には戻りません。

予防策として
・音量は最大音量の60%以下を目安にする
・1時間使用したら10~15分程度耳を休める
・ノイズキャンセリング機能のあるヘッドホンを活用して音量を下げる
・外の音も必要な場面では片耳だけ使用するなど工夫をする。
・耳の不調を感じたら、早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。
治療方法
一度傷ついた内耳の有毛細胞は再生しません。症状が進行すると元に戻らないため、早期発見・早期対策が非常に重要です。
軽度の場合は、使用習慣を見直すことで改善する可能性があります。
進行している場合は補聴器などの対策がとられます。
耳鳴りがある場合は早めに耳鼻咽喉科で診てもらいましょう。
精神的ストレスと耳の病気の関係
突発性難聴やメニエール病など、ストレスと関係が深い耳の病気もあります。
ストレスの多い生活は耳にも負担がかかります。
○きっかけが不明の突発性難聴
外耳や内耳に問題なくてもある日突然、片耳(まれに両耳)が聞こえなくなる病気です。
原因がはっきりしないことが多いですが、最近では過労や睡眠不足・精神的ストレスが発症の要因の一つと考えられています。
早期発見・早期治療がカギ
発症から48時間以内の治療が非常に重要です。治療が早いほど回復率が高くなります。
音が急に聞こえにくくなった、耳がつまった感じがする、耳鳴りが続いている。
こんな症状あればすぐ耳鼻咽喉科へ行きましょう。
○めまい・耳鳴りを繰り返すメニエール病
内耳のリンパ液のバランスが崩れることで、めまい・耳鳴り・難聴を繰り返す内耳の病気です。
30~50代に多く、女性にやや多い傾向があります。
天井がぐるぐる回るようなめまいが突然が起こり、強い疲労感に襲われる人もいます。

ストレスとの関係
塩分を控えた食事、睡眠をしっかりとる、適度な運動をすることでストレス管理をするなど生活習慣の見直しが非常に重要です。
放置すると聴力が低下し慢性的な難聴になることがあります。